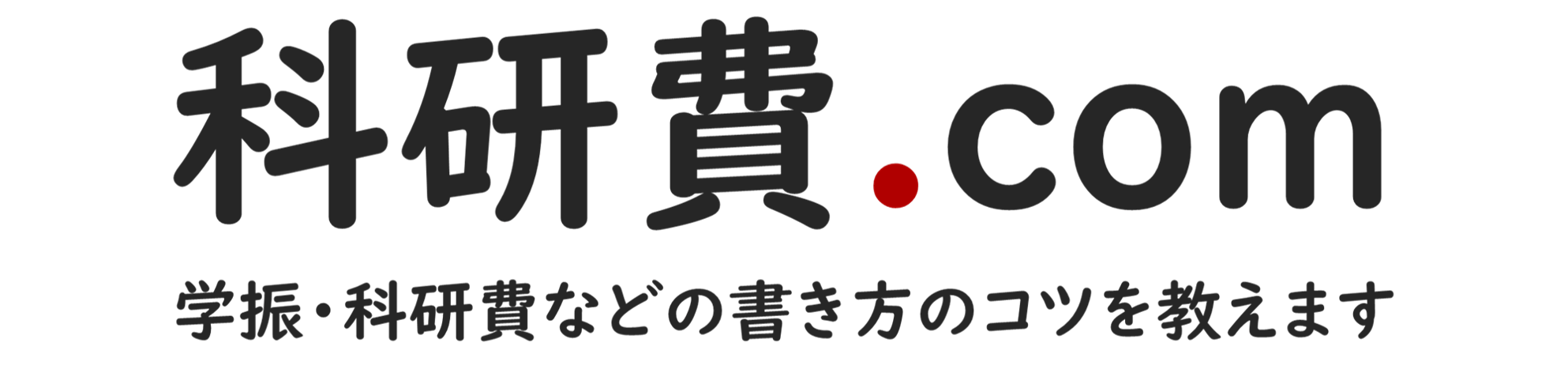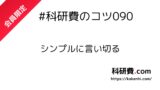間違いなく審査員よりも申請者の方が研究計画の内容を良く知っています。その研究のことを良く知っているはずの申請者が自信のない表現だと、審査員としてはポジティブに評価しようがありません。
言い過ぎを避けようとするあまり、表現を弱めた文章は主張が弱くなり、場合によっては、申請者がやった(発見・発明・考えた)という事実を十分にアピールできません。一方で、言い切るためには、根拠を示さねばならず、必然的に論理的な文章になります。さらに、文末がすっきりとすることで、文章を短くし主張をわかりやすくするという効果も期待できます。
たしかにアルビノ個体を考えれば「ほとんど」をつけることが正しいですが、ここで「ほとんど」をとったところで主張は大きく変わらないばかりか曖昧さが消え、力強く簡潔にメッセージを打ち出すことができます。
また、受動態の文章は、主張が弱くなりがちです。この場合だと、申請者が明らかにした、という事実を受動態では表現しづらく「申請者によって … が制御されることが示された」のように回りくどい文章になってしまいます。
2番目の例のように能動態にして言い切る方がわかりやすさという点では優れています。このままでも、おそらく申請者が明らかにしたであろうことは予想できますが、3番目のように「誰が示した」かを明示するとさらに主張がはっきりします。
人によってはくどい、癖の強い表現と感じるかもしれませんが、日本人の文章は控えめであることが多いので、その中では目立つと思います。
英語論文でも通常は受動態で書きますが、NatureやScienceクラスになると意識的に能動態の割合を増やすと言われています。こうすることで、「私(たち)が」やったということをアピールしています。
同様に、一般的な事実についても言い切らないために、回りくどい文章になっている場合があります。
実際にあった良くない表現集
〜は重要であるといえる。
→ 〜は重要である。
申請者らの仮説が正しいことが示唆されたと言える。
→ 申請者らの仮説の正しさが示された。
本研究により、〇〇〇ができれば、〇〇〇に着手できると期待できる。
→ 本研究により、〇〇〇を明らかにすることで、〇〇〇を実現する。
~なのではないかと思われる。
→ ~である。 or ~だろう。
~することかできる。
→ ~できる。
〇〇〇しているのかを検討していくことは喫緊の課題だと言えるだろう。
→ 〇〇〇の検討は喫緊の課題である。
また、否定形の表現は肯定形の表現に直しましょう。
多くない → 少ない
矛盾はない → 妥当だ