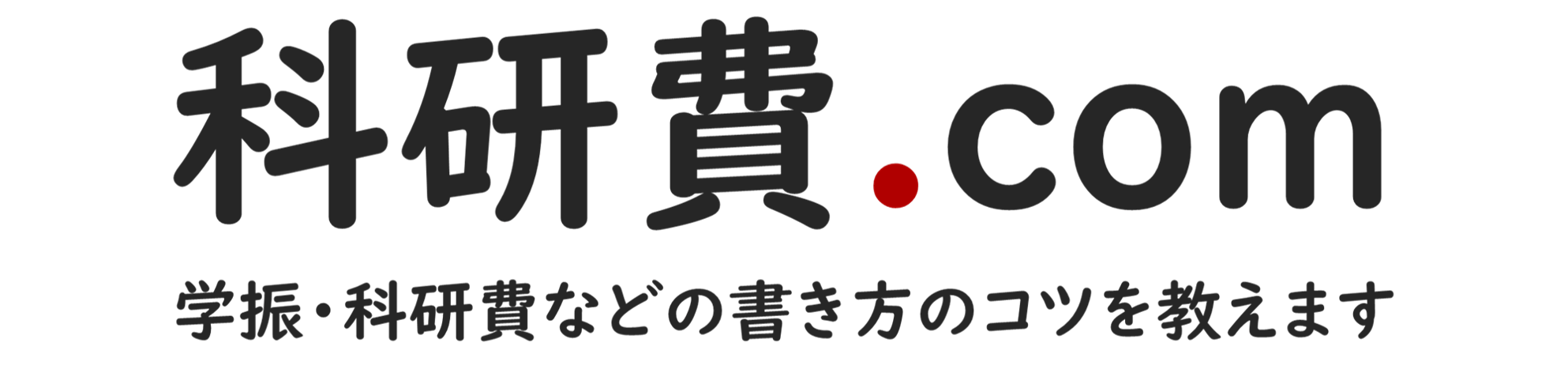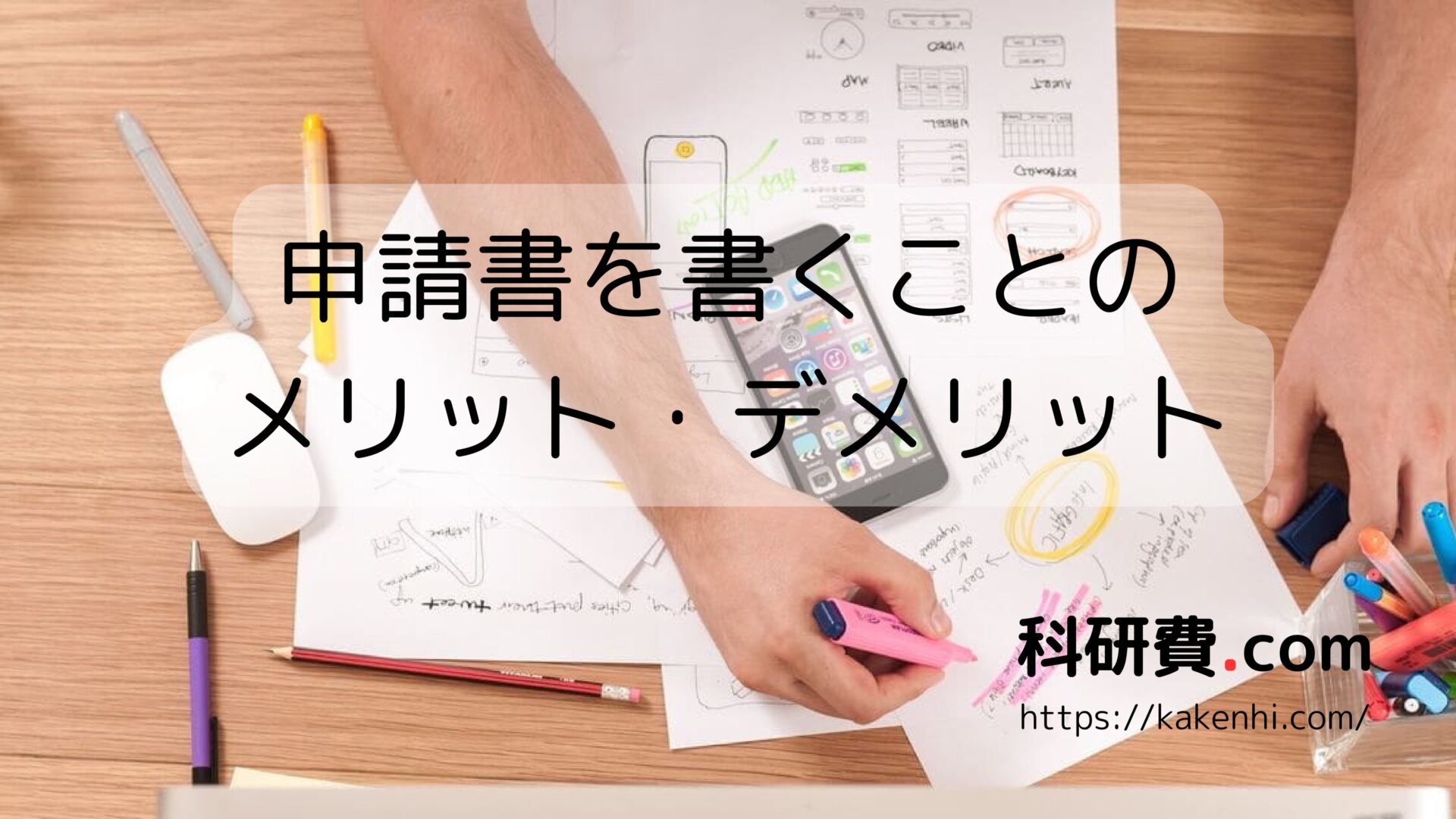メリット
研究が前に進む
ほとんどはこれに尽きます。研究費が無いと始まりません。やりたい研究を前に進めるためにも積極的に研究費を獲得しましょう。
買いにくいものが買える
科研費の場合、購入できる物品に制約がかかる場合があります。民間財団の助成金はかなり自由度が高く、学会年会費なども支払うことが可能になります。自由度の高いお金として、重宝します。
寄付金控除(所得控除)・公益社団法人等寄附金特別控除(税額控除)
民間財団から得た助成金の一部は個人口座を経由して大学に寄付するというスキームが取られることがあります。こうした場合、個人からの大学への寄付金は所得税またはの寄付金控除の措置を受けることができます。寄付金控除には2種類あり、「税額控除」「所得控除」のいずれか一方の制度を確定申告の際に選択します。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)やふるさと納税などによっても所得税額が変化し、場合によっては十分な控除が受けられなくなる可能性があります。
税制は常に変化しますので、最新の情報をチェックしてください。
No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|国税庁 (nta.go.jp)
No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき|国税庁 (nta.go.jp)

助成金のボリュームゾーンである100万、200万円を考えるとどちらを選択すべきかはかなり状況によります。制度を良く理解し、お得な選択をするようにしましょう。
公益社団法人等寄附金特別控除(税額控除)
寄付金額(所得の40%が限度)から2,000円を差し引いた額の40%を所得税額から控除する。
| 寄付金額 | 課税所得金額 400万円 | 500万円 | 600万円 | 700万円 | 800万円 | 900万円 | 1,000万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10万円 | 39,200円 | 39,200円 | 39,200円 | 39,200円 | 39,200円 | 39,200円 | 39,200円 |
| 20万円 | 79,200円 | 79,200円 | 79,200円 | 79,200円 | 79,200円 | 79,200円 | 79,200円 |
| 50万円 | 93,125円 | 143,125円 | 193,125円 | 199,200円 | 199,200円 | 199,200円 | 199,200円 |
| 100万円 | 93,125円 | 143,125円 | 193,125円 | 243,500円 | 301,000円 | 358,500円 | 399,200円 |
| 200万円 | 93,125円 | 143,125円 | 193,125円 | 243,500円 | 301,000円 | 358,500円 | 441,000円 |
寄付金控除(所得控除)
寄付金額(所得の40%が限度)から2,000円を差し引いた額を、所得(課税所得金額)から控除する。
| 寄付金額 | 課税所得金額 400万円 | 500万円 | 600万円 | 700万円 | 800万円 | 900万円 | 1,000万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10万円 | 19,600円 | 19,600円 | 19,600円 | 21,000円 | 22,540円 | 22,540円 | 32,340円 |
| 20万円 | 39,600円 | 39,600円 | 39,600円 | 41,100円 | 45,540円 | 45,540円 | 65,340円 |
| 50万円 | 99,600円 | 99,600円 | 99,600円 | 101,100円 | 114,540円 | 114,540円 | 164,340円 |
| 100万円 | 169,800円 | 199,600円 | 119,600円 | 201,100円 | 229,540円 | 229,540円 | 329,340円 |
| 200万円 | 229,800円 | 369,800円 | 399,600円 | 401,100円 | 431,100円 | 459,540円 | 559,540円 |
住民税の寄附金税額控除
特定の法人や機関、団体に寄附をしたときに住民税の優遇を受けるという制度で、寄附を行った翌年度の住民税で控除が行われます。
ただし、以下の法人への寄附金は、各都道府県や各市区町村が個別で指定している機関でないと住民税の寄附金控除の対象とすることはできません。つまり、住んでいる都道府県や市区町村で指定されていない寄附金の場合は、所得税の減額は行われますが、住民税の減額は行われません。
- 国公立大学法人
- 独立行政法人
- 特殊法人
- 公益財団法人
- 公益社団法人
- 学校法人
対象となる寄附金かどうかは、都道府県や市区町村のホームページで確認することができますが、自治体によっては記載していないところもありますので、その場合は直接問い合わせをしましょう。
都道府県をまたぐと対象から外れるケースもあります。
所属機関からの報奨金・給与がもらえる
学振は給与(研究奨励金)がもらえますし、研究機関によってはある程度以上の外部資金を獲得した教員に報奨金を出しているところもあります。
特に学振において自分で給与を持っていると雇用主の意向に左右されずに研究を続けやすくなりますので、積極的に狙っていきましょう。受け入れ研究室としても人件費がかからないため、博士研究員(ポスドク)として受け入れやすくなります。
内容のブラッシュアップ・効率化
申請書を上手に書くためには何度も繰り返して書くことです。また、ある程度うまくいった実績のある申請書をベースにすることで、効率よく、高品質の申請書を作成することも可能になります。
普段から、データや構想をまとめておき、こまめに応募しておくと、(多くの人にとって本番である)学振や科研費の申請書をうまく書くことができるようになります。
デメリット
作成に時間がかかる
慣れないうちは、ひとつの申請書を書くのに相応の時間がかかってしまいます。金額の小さいものについては作成の手間が惜しいと感じる場合もあるかもしれません。
しかし、カバーする範囲を変えた申請書を3パターンくらい(基礎、応用、異分野融合など)用意できるようになると、次回以降の申請時にはそれらをテンプレートとして使いまわすことが可能になります。もちろんずっと使い続けるわけにはいかず、状況に応じて大幅な改稿も必要となりますが、それでもかなり楽になるはずです。
報告書に時間がかかる
申請書は使いまわしやすい一方で、報告書は使いまわしにくいです。そのため、数多くの助成金を得ると、そのぶんだけ、報告書を書かないといけなくなり、大変です。しかし、お金がない苦しさと比べると贅沢な悩みですので、感謝しながら書きましょう。
エフォートがなくなる・重複制限が発生する
また、民間財団であってもエフォートを書く必要があります。政府系の研究費ほどはちゃんと把握されていないとはいえ、虚偽の説明が明るみに出ると大変です。エフォートは下げることは可能ですので、適切に管理し、もっとも応募したい研究費のためのエフォートは取っておくようにしましょう。
また、ある研究費に採択されると他の研究費に応募できなくなる・受給できなくなる、重複制限もあります。これと年齢制限や期間限定応募などが重なってくると、出したいのに出せないといった状況が発生してしまいます。突発的なものはしょうがないにせよ、見えているものについては計画的に応募するようにしましょう。