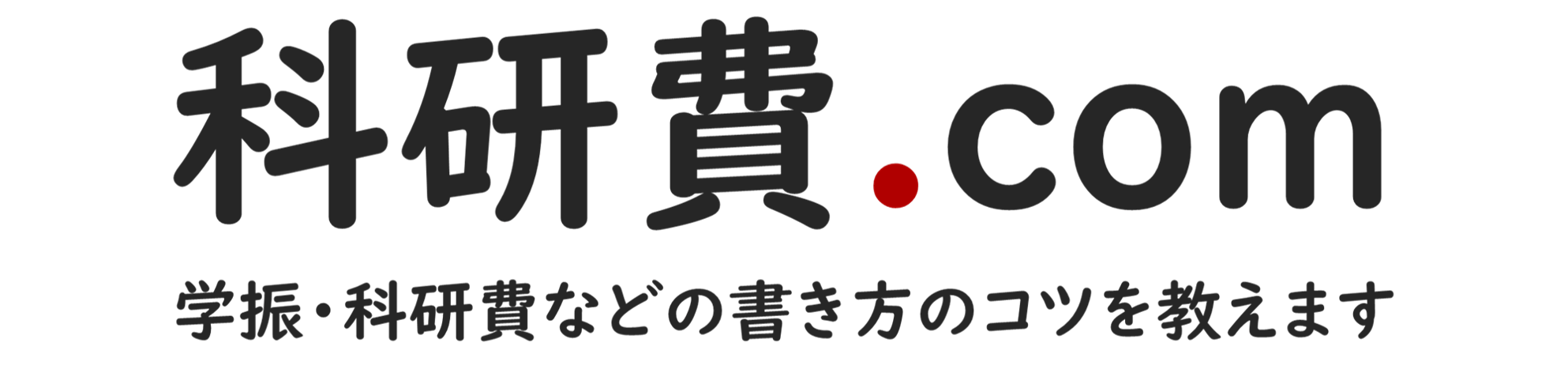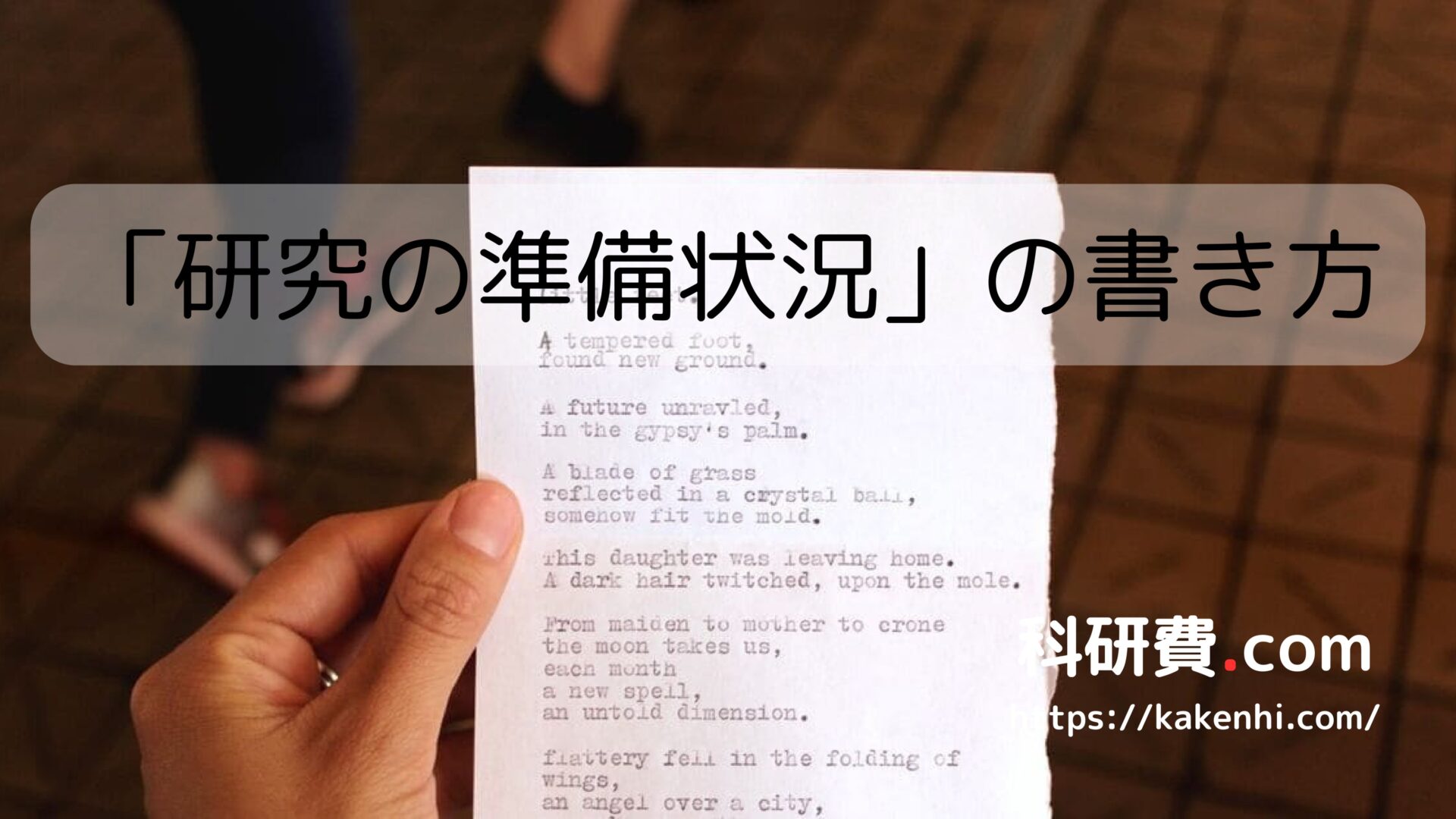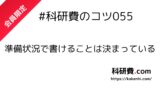研究の準備状況とは、本研究を進めるための準備がどれくらい整っているか、研究スタート時にどれくらい整っていそうかを書くための欄です。たくさん書く必要はなく「準備ができている、問題ない」と手短に答える一択です。
研究目的、研究計画などには、以下の内容が含まれます
1. 本研究で何を明らかにするか(研究目的)
2. どうやって明らかにするかの概要
3. 研究目的を達成するための具体的な2,3の研究項目
3-1. (計画の背景・問題点のリマインド)
3-2. 何をどうるすのか
3-3. 具体的な研究のゴール
3-4. 予備データ、計画を理解できる図
4. 予想通りに行かないときの対応
5. タイムテーブル
6. 研究の準備状況
たとえば、研究計画が採択されてから研究材料や研究装置を作り始めたり、調査対象の選定を始めたりするようでは、研究の本気度を疑われかねませんし、研究をスムーズに開始できるとは言えません。「そうしたことはない、申請者は本気で研究を進めようとしっかり準備している」と主張するためには、準備状況を審査員に示す必要があります。
研究の準備状況で示すべき内容
- 材料の準備、手法の検討などを終えており(着手しており)、スムーズに研究を開始できる、あるいは、研究開始時までに準備が終わる見込みである。
- 研究協力者、分担者、共同研究者とのコミュニケーションが十分に取れている。
- 調査の協力施設、検体・サンプルの確保、資料の準備などの見込みが立っている。
- 各種申請・許可・審査などが完了しているか進行中である(「人権の保護及び法令等の遵守」と重複しない範囲において)
- すでに一部の実験を開始しており、本研究開始時に必要となる情報が得られる見込みである。
など、「だから、本研究は採択後、速やかに実施できる」という主張につながるような内容を書きます。
研究環境との違い
似たような内容を書く欄として研究環境があります。研究環境では、研究遂行の前提となる施設・設備の状況やエフォート、人員など、文字通りの意味で研究そのものを実施するための環境について書きます。一方で研究の準備状況では、材料がある、すでに始めている、予備データがあるなど他の研究ではなく「本研究」を実施するための準備状況について書きます。
ここはそれほど書くことはなく、「準備は整っている」という内容でせいぜい5-10行も書けば十分です。他で書くべき内容を含む形でダラダラと書かないよう、そして、研究環境と同じ内容を繰り返して書かないように気を付けてください。